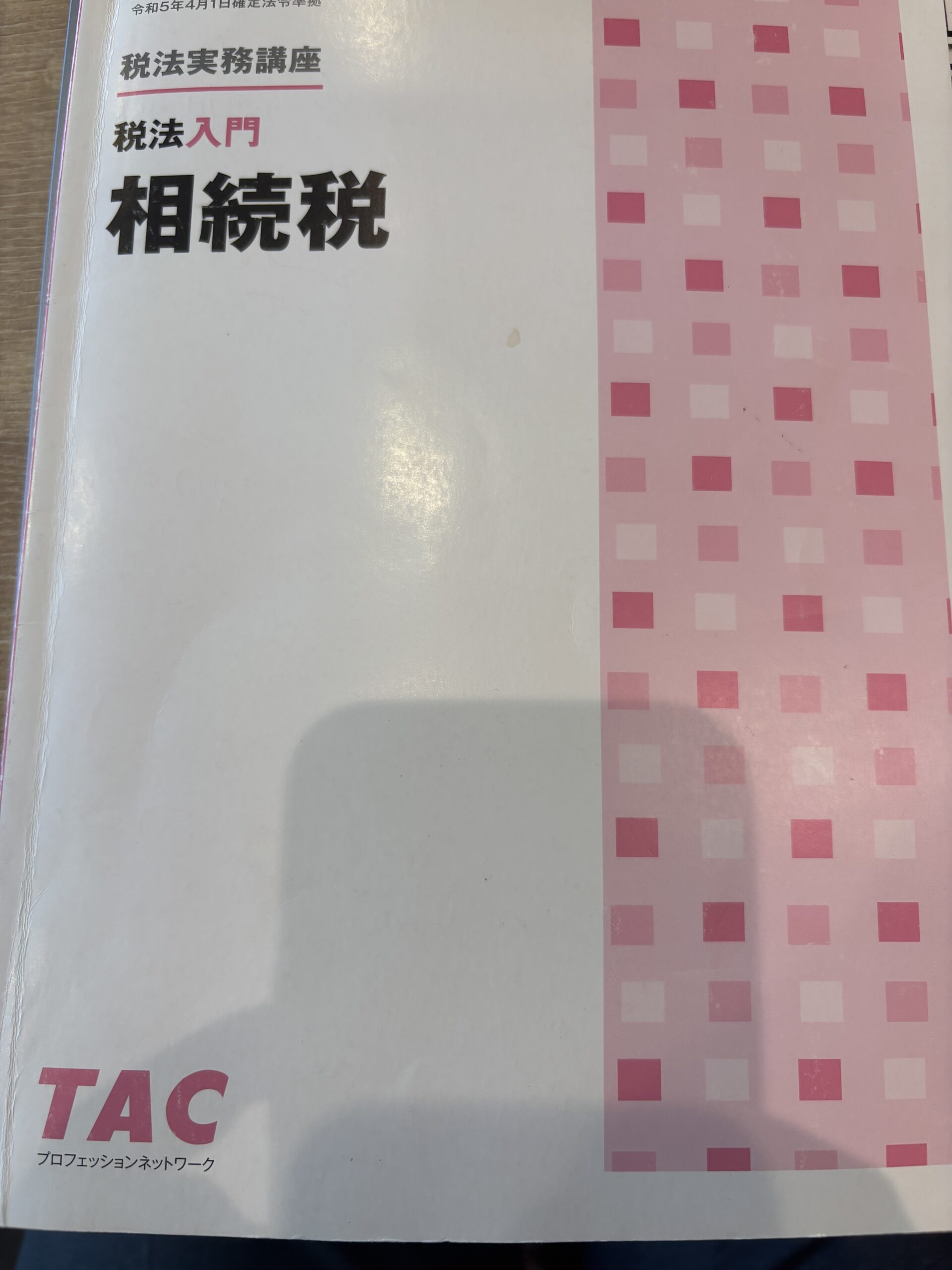被相続人が住んでいた自宅の土地や、事業を営んでいた土地を相続した場合、その評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」というものがあります。
これは、残された相続人の生活や事業の基盤を守ることを目的とした制度です。
今回は、この特例について解説します。
限度となる面積と減額の割合
小規模宅地等の特例は、対象となる土地の種類によって、減額できる面積の上限(限度面積)と減額される割合が異なります。
| 宅地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
| 被相続人の居住用 | 330m²(約100坪) | 80% |
| 被相続人の事業用 | 400m²(約121坪) | 80% |
| 被相続人の賃貸事業用 | 200m²(約60坪) | 50% |
具体例
【被相続人の居住用の例】
被相続人が住んでいた自宅の土地の評価額が5,000万円、面積が250m²だったとします。
この場合、限度面積が330m²以下なので、評価額の80%を減額できます。
5,000万円×80%=4,000万円
この特例を適用することで、相続税を計算する際の土地の評価額は1,000万円(5,000万円 – 4,000万円)となり、大きく相続税額を軽減できます。
相続税が算出されない場合も申告しないといけない
小規模宅地等の特例は、自動的に適用されるわけではありません。
この特例を受けるには、相続税の申告書にその旨を記載し、必要書類を添付して提出する必要があります。
たとえ、この特例を適用した結果、支払うべき相続税額がゼロになったとしても、申告書の提出は必要になります。
もし申告を怠ってしまうと、特例は認められず、多額の相続税を支払わなければならなくなるので要注意です。