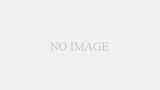相続が発生する前の3年間(2024年1月からは7年間)に相続人に贈与したものは、その贈与はなかったものとされてしまいます。
例えば、5,000万円の財産を持っている方が、100万円の贈与を3年間行った後に亡くなった場合は、普通に考えると残りの財産は次のようになります。
5,000万円ー300万円=4,700万円
しかし、相続税の対象となる遺産額は、4,700万円+300万円=5,000万円となります。
つまり、亡くなる前に贈与した300万円の財産が「加算」されてしまうのです。
孫へ贈与する
この「加算」されるルールの対象となるのは、原則として、将来相続人になる人に対する贈与に適用されます。
例えば、父、母、長女(孫)、の4人が登場人物で、仮に、父に将来相続が発生することとした場合の相続人は、母と長女です。
つまり、孫は相続人ではないので、孫への贈与は亡くなる1日前に行った場合でも相続税の節税効果を受けることができます。
同じように、長女に配偶者がいた場合に、その配偶者に生前贈与した財産も加算されることはありません。
長女の配偶者は相続人には当たらないからです。
しかし、もし長女が離婚した場合は、長女の元配偶者に贈与した財産は戻ってきませんので実務上は取り扱いは少ないようです。
まとめ
余裕資金があり、まだまだ元気であれば、子供・孫、双方に贈与する方が良いでしょう。
長生きできるのであれば、少しずつ財産を贈与して節税効果も大きくなります。
一方、3年(7年)以内に相続が発生するかは誰にも分かりません。
今回の解説で示したように、孫や子の配偶者への贈与、という選択肢もありますので参考にしてください。