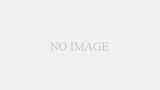アパートやマンションを購入すると相続税の節税になる。
こんな話を一度は聞いたことがあると思います。
今回は、何故、不動産を購入すると相続税が減るのか、について解説していきます。
不動産の時価を個人が把握することは困難
相続税という税金は、亡くなった方が残した遺産の「相続発生時点の時価」を基準に計算します。
遺産が現金や上場企業の株式であれば、時価があるので相続税の計算はそんなに難しくはありません。
しかし、不動産は簡単に時価は分かりません。
時価を把握しようと思ったら、不動産屋さんに「今、売ったらいくらになるか」と、見積もりを取ったり、不動産鑑定士に依頼すれば客観的な数字を出してくれます。
でも、お金も時間もかかりますので容易ではありません。
そこで国は、誰でも簡単に不動産の時価を算出できるよう「路線価方式」というものを公表しています。
誰でも時価がわかるように:路線価方式とは
路線価方式とは、国が日本の主な市街地の道路1本1本に値段(路線価)を振り、その道路に接している土地の面積(1m2)×路線価をすれば、誰でも簡単に土地の時価を算出できるという方法です。
この方法で計算された土地の価格のことを相続税評価額と言います。
この相続税評価額は、実際に売買される価格を10とすると、相続税評価額は8程度で低く抑えられています。
では何故、国は2割も低く評価することを認めているのでしょうか。
路線価方式は、簡単に評価額を求めることができる半面、正確性は高くありません。
また、路線価は年に一度しか更新されませんが、不動産の時価は、1年の間で大きく変動します。
もしも、実際の時価よりも高い評価額で課税してしまった場合には、国は納税者から訴訟を起こされるリスクがあります。
そのような事態を避けるためにも、実際の価格よりも2割程度低めに路線価を設定しているのです。
そして、この時価と評価額の差を利用すると、相続税を大きく節税することができるのです。
1億円の現金で1億円の土地を買ったらどうなる
例えば1億円の預金を持っていたとします。
何もしなければ相続発生時には、この1億円の預金に相続税がかかることになります。
では、この1億円の預金で1億円の土地を購入した場合はどうなるでしょうか。
先ほどの路線価方式を使うと、相続税評価額は2割低くなるので、8,000万円に対して相続税がかかることになります。
さらに、その土地を自宅として使うのではなく、土地の上にアパート等の賃貸用建物を建築した場合には、土地の評価額をさらに2割ほど割り引いて評価して良いこととされています。
先ほどの土地であれば8,000万円の2割引き、つまり6,400万円で評価されることになるのです。
建物の場合は?
建物の相続税評価額は、固定資産税の通知書に記載されている固定資産税評価額をそのまま使います。
この固定資産税評価額は建築価格(時価)の約7割になるように設定されています。
そのため、仮に1億円かけて建物を建築したら固定資産税評価額は7,000万円になります。
さらに、その建物を自分で使うのではなく、アパートなどにした場合は、固定資産税評価額から3割引きした金額が相続税評価額となります。
7,000万円の3割引で4,900万円。
1億円の預金でアパートを建築すると、相続税評価額は4,900万円になるのです。
このように土地や建物のような不動産は、相続税の評価額はこのような理由で低く抑えられることになります。